1.大学に例えると
法律系の国家資格のひとつで、
大学に例えると、
司法・予備試験が東京大学ならば、
行政書士試験は、
明治、青山、立教、中央、法政大学群 のようです。
2.起源は諸説
行政書士の歴史をたどると、
(1)「史(ふびと)」という朝廷(政治を行うところ)で文書作成の職務にあった人々という説。
(2)江戸時代に、市井(町)の有識者(武士、名主、住職等)による代書・代筆という説。
(3)「町内書役」という説。
(4)目安箱へ苦情申し出のための代書という説。
など諸説ある。
3.法令が制定
江戸時代も中期頃になると、貨幣経済が農村へ浸透し、土地境界や金銭争い等も増加する。
幕府はこれらの事態に、裁判方式を導入するため、「公事方御定書・御定書百箇条(法令)」を制定する。
4.奉行所
明治憲法制定までは、行政官庁も司法官庁も一体化してまとめられ、行政、警察、裁判の機能を全て行政役所である「奉行所」が運用していた。
5.「公事(くじ)」
現在の民事裁判に当たる「出入筋(でいりすじ)」、裁判を、「出入物(でいりもの)」又は「公事(くじ)」と呼んでいた。
ここに、「公事宿(くじやど)」とは、裁判のため遠方から来た人の宿泊所で、そこの主人らが必要書類の代書をしていたとされている。
このように、書類の普及で、「奉行所」に提出する書類を庶民に代わり作成するようになる。
6.「願」
また、「奉行所」に対し、行政的な施策に対するお願い事である「願」の題目があり、町村民、町村役人等から郡代・奉行所へ各種の「願事」があったとされる。
例えば、嘆願・請願、許認可願、措置の許可等(「立木払い下げ願、開墾願、拝借願、株の譲渡願」)が「願」であり、事業や当該行為の許諾のことであった。
7.書面
こうした行為は、現代の行政書士から見た場合、行政役所に提出する書面であり、
依頼人のために代書業務を行い、この「願」に対する代書、つまり、官と民とを結ぶ「代書」行為が、明治期の代書人へと繋がっていくことになる。
8.太政官布告
1872年(明治5)年8月3日の太政官布告(だじょうかんふこく)として「司法職務定制」が発せられ、
その中に「証書人」(現、公証人)、「代言人」(現、弁護士)、代書人(現、司法書士・行政書士)という職制が創設された。
9.事務・法定弁護士
「代書人」と「代言人」の制度は、英国の「事務弁護士」と「法廷弁護士」の二元主義的弁護士制度を導入したようで、
「代書人」は、英国の「事務弁護士」に対応するものであった。
10.分岐
代書人制度で、裁判書類の作成をしていた代書人が司法書士になり、
その他一般文書や市町村役場、警察署等に提出する書類の作成をしていた代書人が行政書士になっていく。
代書人は裁判所や行政機関の窓口的、補助的役割を期待されていた。
11.三者の役割
このように、証書人、代言人、代書人の三者の役割が、明治時代後期以降、明確になっていく。
12.各法令制定
その後、明治36年以降に「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められ、
1919年(大正8年)4月9日、司法代書人法(現、司法書士法)が制定、
翌1920年(大正9年)11月25日内務省令第40号に(行政)代書人規則(現、行政書士法)が制定される。
13.再構築
司法手続は弁護士と司法代書人に、
行政手続は、行政代書人に再構築された。
14.国家試験
現在、司法書士、弁護士、行政書士は、
各法律専門職として国家試験によって能力が担保され、その業務分野の専門家として、
15.第1条 「使命」
司法書士法第1条「国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与する」
弁護士法第1条「基本的人権を擁護し社会正義を実現する」
行政書士法第1条「国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資する」
とそれぞれの業務領域で独自の方向に進化を遂げ、「法律道」を胸に秘め、社会貢献に邁進している。
どこに聞けばいいか
まずはご相談、お問い合わせください。
9:00~17:00
土日祝日も相談
・研修会、出張等で
臨時休業あり
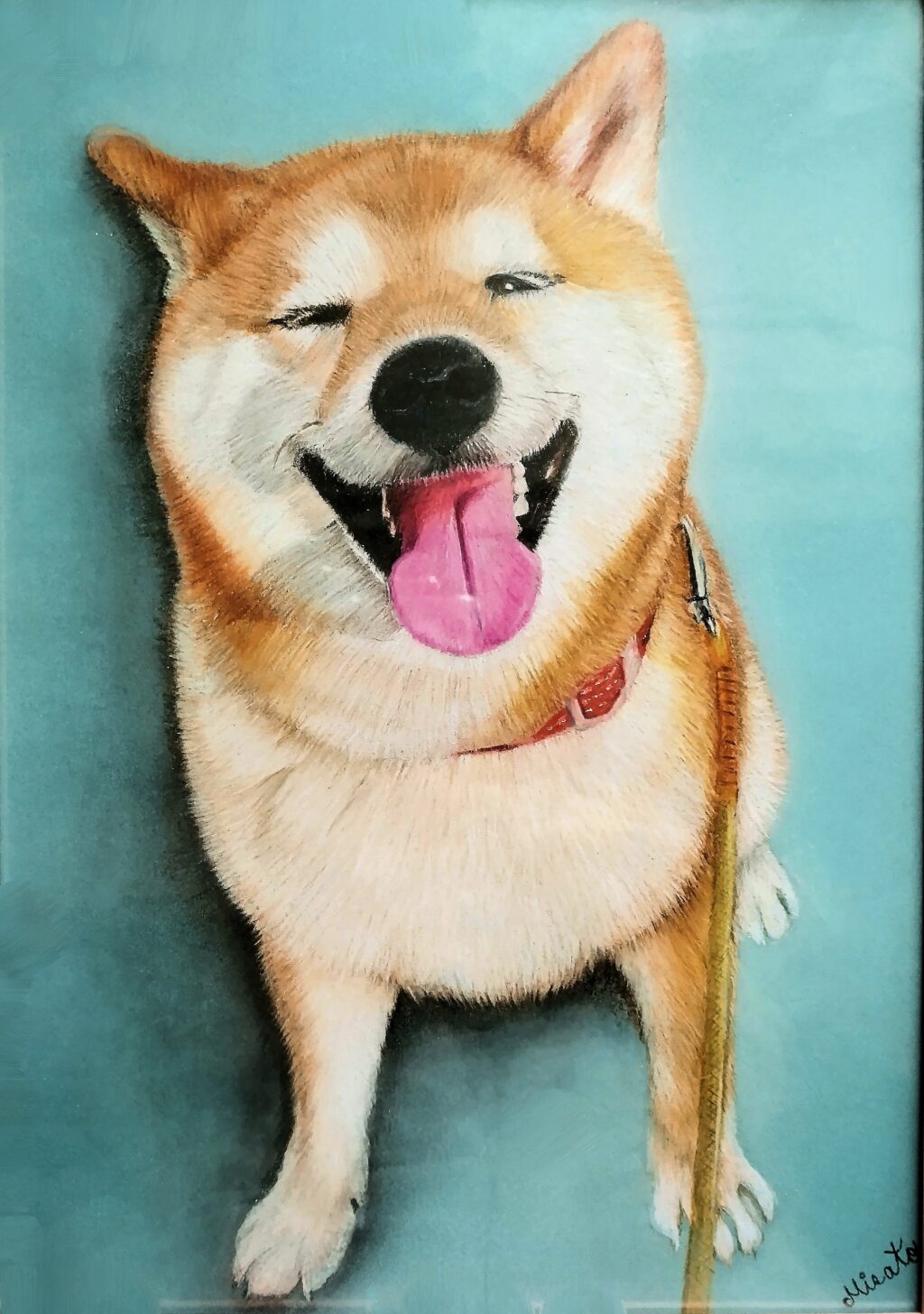

絵:「にじいろの手」