1.手続きの流れ
- (1)事前準備
- ・支援者として、任意後見受任者を本人が自由に決めることができ、家族、知人または、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家など候補を思案。任意後見人になるための資格は必要ありません。
・契約内容(即効型、移行型、将来型)
- (2)契約締結
- ・本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と任意後見契約を締結。公正証書による作成が必要です。
・必要に応じて任意後見監督人候補者も記載(移行型では、委任契約に「任意監督人の選任請求義務」の明記)。
・取消権行使の記載
・公証人から任意後見契約の登記が法務局に依頼される。
・生活、介護、療養について
・お金の使い方や不動産など財産の活用、処分、利用について
・任意後見人の報酬や経費について
・任意後見人に依頼する事務(代理権)の範囲について
- (3)本人の判断能力の低下
- ・速やかに任意後見監督人の選任手続き
- (4)任意後見監督人の選任の申立て
- ・申立人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申し立てる。
- (5)任意後見開始
- 任意後見監督人の選任したときから、任意後見が開始され、任意後見人が後見事務を開始(任意後見受任者が任意後見人となる。)。
2.業務内容と費用・報酬(税抜)
※相談顧問料:受任契約業務完了後から、1か月間(月額30,000円)無料
| 業務内容 | 報酬額 |
| 任意後見人制度 (公正証書)の利用支援 | 100,000円~ |

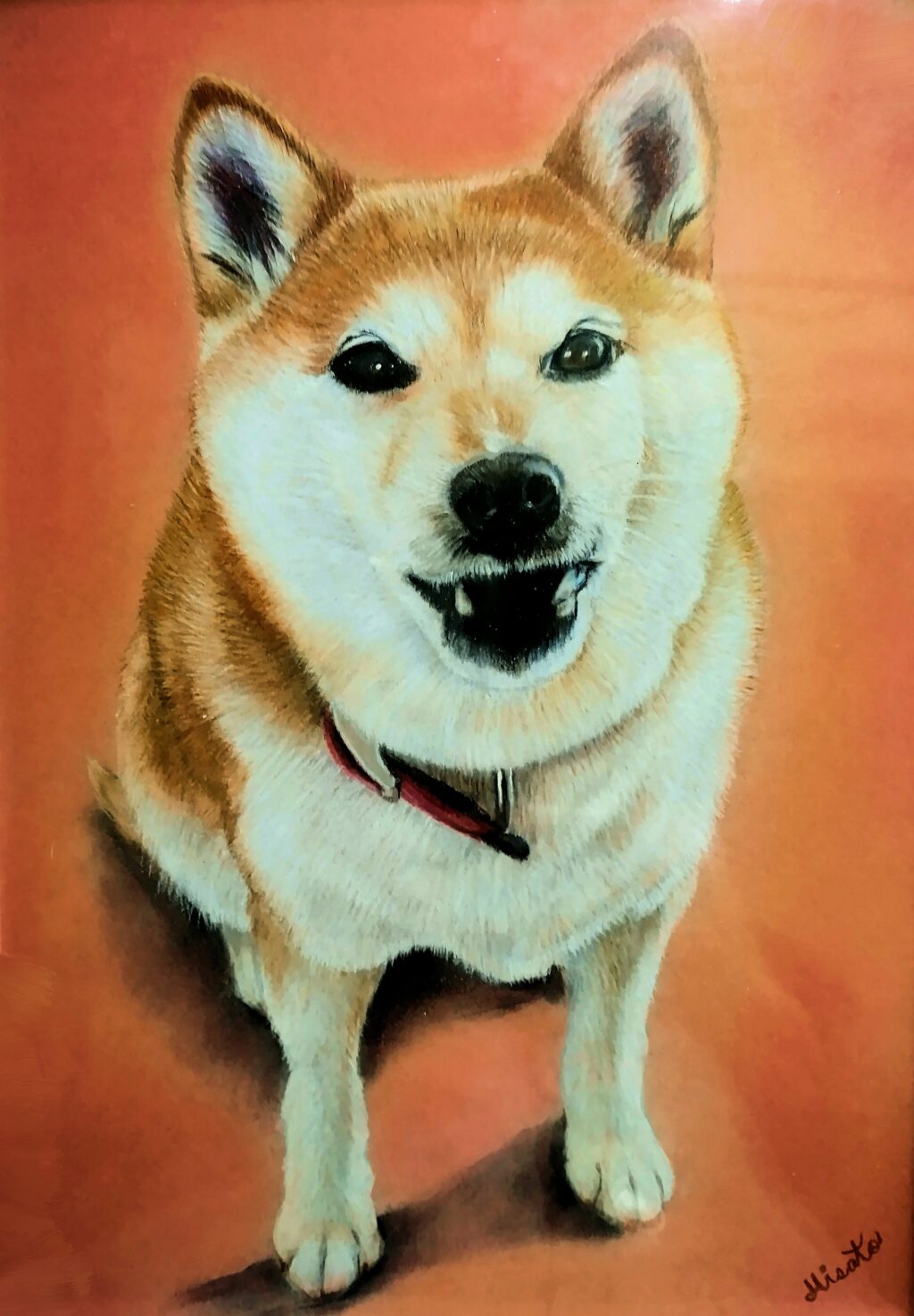
絵:「にじいろの手」
どこに聞けばいいか
まずはご相談、お問い合わせください。
9:00~17:00
土日祝日も相談
・研修会、出張等で
臨時休業あり